- 不動産売買の仲介手数料の売上高の計上日は原則売買契約が締結された日、継続適用を前提に契約に係る取引が完了した日です。
- 不動産売買の仲介手数料の売上高の計上日基準を変更するためには合理的な理由が必要になります。
- 節税だけを考えるなら不動産仲介業者の決算時期は3月末以外が良いです。
不動産売買の仲介手数料の計上時期について
不動産売買の仲介業を営む会社から「仲介手数料の売上高の計上日基準を変えれば、翌期に売上高を繰延べられますか?」とたまに質問を受けます。
恐らく、期末に多額の利益が計上される予想になり、なんとか節税できないかと調べたところ、以下の法人税基本通達を見つけたのでしょう。
土地、建物等の売買等の仲介をしたことにより受ける報酬の額は、原則として、その売買等に係る契約の効力が発生した日の属する事業年度の益金の額に算入する。
ただし、法人が、売買等の仲介をしたことにより受ける報酬の額について、継続して当該契約に係る取引の完了した日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める。引用元: 法人税法基本通達2-1-11
簡単に言うと、不動産仲介業を営む会社の仲介手数料の売上高の計上日基準は以下のようになります。
- 原則⇒売買契約が締結された日
- 例外⇒不動産の引渡し日(継続適用を前提)※
※ 不動産の引渡し日とは、建物の場合は鍵の引渡し日、土地の場合は土地譲渡承諾書の交付日で、基本的には決済日と一致します。
不動産売買取引は3月末に多い
一般的な会社の決算日が3月末に集中している影響で、利益調整や損失回避のため、不動産売買取引を3月末までに行いたい会社は多いです。
そのため、3月末を不動産仲介業を営む会社の決算期にしておくと、不動産売買契約日が3月下旬で、不動産の引渡し日が4月上旬のようなちょうど決算期を跨ぐ取引が発生したりします。
また、不動産の売買取引の仲介手数料は、売買金額の片手で3%程度、両手で6%程度なので、売買金額が高ければ高い程、期末間際で多額の仲介手数料が売上高として計上されることになります。
売上計上日基準を変更するには理由がいる
不動産仲介料の売上高の計上日基準は税務上の論点になるところです。
売上高の計上日基準を簡単に変更できれば、利益調整につながる可能性が高く税務署も厳しくチェックしています。
だから、上記の法人税法基本通達2-1-11でも、引渡し日基準を採用したのならば継続適用することを求めています。
もし、あなたの会社が設立第1期目だとしたら、法人税の申告書を税務署にまだ一度も提出していない状態のはずです。
その場合には、売上高の計上日基準を誰にも公表していないので、第2期目以降も継続することを前提に、不動産の引渡し日をもって仲介手数料の売上高を計上することも可能でしょう。
しかし、あなたの会社が設立2期目以降ならば、前年度までの売上高の計上日基準と当年度の売上高の計上日基準を変更することは税務上リスクが高くなります。
前年度までは、売買契約の締結日に不動産仲介料を売上高に計上をしていたのに、当年度からは、不動産の引渡し日に不動産仲介料を売上高に計上しはじめた場合、売上高の計上日基準の変更になるので、「変更する合理的な理由(根拠)」が必要になると考えられます。
では、合理的な理由(根拠)とはなにかというと、現状採用している売上高の計上日基準より変更した方がより取引の実態を反映できる理由です。
例えば、不動産売買取引を締結し終えた後、引渡し日(=決済日)までに契約が破談した場合は、仲介手数料を受け取れないのが通常の契約内容であれば、不動産の引渡し日(決済日)に売上高を計上する方が実態に合っているので、契約締結日基準から引渡し日基準に売上高の計上日基準を変更しても問題ないはずです。
いずれにしても、不動産仲介料の売上高の計上日基準を契約締結日基準から引渡し日基準に変更することは、どうしても売上高を翌期に遅らせるための節税手法という印象が強いですので、変更をする際には細心の注意を払うことが必要でしょう。
ただし、禁止されているわけではないので、どうしても節税したいというのなら、取引先や自社の状況に合わせて売上高の計上基準の変更の合理的な理由を考えてみてください。
不動産仲介業を営む会社の決算期は3月末以外が良い
不動産売買取引は3月末に多いということは前述の通りですが、もしこだわりがなければ、決算期変更をして、不動産仲介業を営む会社の決算期を3月末以外にした方が良いでしょう。
理由は節税目的で2つあります。
- 期末間際の急な売上高でなければ、保険加入や決算賞与などの節税対策をとれる可能性が高い
- 買主・売主の会社と決算期がずれていれば、不動産売買契約日の後倒しをお願いすることにより、売上高の計上基準日に関係なく、仲介手数料を翌年度の売上高に計上できる可能性がある
保険加入や決算賞与などの節税対策を行うには、相当な準備期間が必要になります。
仮に、3月末に急な不動産売買による仲介手数料の売上高が生じても、4月末決算であれば、1か月の準備期間が取れるので、節税対策を行い易くなります。
一般的に、不動産売買を行う買主と売主が3月末までの駆け込み売買を依頼してくることは非常に多いので、不動産売買の仲介業を営む会社が節税対策を行うためには、3月末以外の決算日にしておいた方が準備期間が長く取れ、不動産仲介業を営む会社にとって有利に働きます。
また、不動産売買を行う買主と売主が3月末までの駆け込み売買を依頼してくることが多いということは、その時期は買主・売主共に当年度の経営成績を非常に気にしている期間ということになります。
よって、翌年度の経営成績になってしまう4月への不動産売買契約の後倒しを嫌い、仲介会社から契約希望日を提示することは非常に難しいということになります。
逆に、決算月である3月末以外であれば、買主・売主共に不動産売買契約日をさほど気にしない場合も多いです。
つまり、例えば、不動産仲介業を営む会社の決算日が7月末で、7月31日に不動産売買契約を行う予定でしたが、買主・売主と交渉して、8月1日に契約を後倒しに出来れば、売上高の計上基準日が契約締結日基準でも翌期の売上高に堂々と計上できることになります。
買主・売主の意向もあるので、毎回出来る方法ではないですが、事前に交渉しておけばすんなりOKしてくれる取引先も多いはずです。
上記2つの節税目的の達成のため、決算期変更を勧めていますが、決算期変更自体は簡単にできます。
もし、あなたの会社の決算日を変更する場合、過去の経験から一番不動産売買の仲介実績が少ない月を決算期に変更すれば、節税対策に繋がる可能性はさらに大きくなるでしょう。



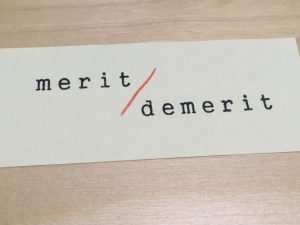







コメント