
- 建物の購入した場合に、少しでも多くの経費を計上したい人
- 建物と建物付属設備の耐用年数の違いを知らない人
- 建物を利用した節税対策の方法を知りたい人
賃貸用不動産を購入する場合、土地・建物の売買価格は不動産売買契約書で一括して表記されるため、少しでも建物の価格を多くできれば、減価償却を通して、より多くの経費を計上できるというお話を「不動産取得時に優位な土地・建物の按分割合を設定して節税を目指す方法!」でしました。
今回は、さらに一歩進んで、建物を躯体部分と付帯設備部分に区分すればさらに経費を多く計上できるというお話をします。
躯体部分と付帯設備(建物附属設備)とは?
躯体部分というのは、柱、天井、床に相当する部分など、建物そのもののことをいいます。
付帯設備とは電気設備、給排水設備、衛生設備(お風呂、洗面所、トイレなど)、ガス設備などです。
付帯設備は税法上、建物附属設備と呼ばれるため以下では建物附属設備で統一します。
建物と建物附属設備の減価償却について
減価償却とは、建物や建物附属設備の実際の使用に伴って消耗する部分を、税法上も一定の割合で年々把握して、建物価額や建物附属設備価額を少しずつ経費に振り替えていこうという制度です。
計算方法を示すと以下のようになります。
上記計算式から分かる通り、耐用年数と呼ばれるところが短ければ短いほど、減価償却費として経費計上できる金額は多くなります。
建物の耐用年数は木造の場合22年、鉄骨の場合34年、RCの場合47年と軒並み長い年数が定められています。
それに比べて、建物付属設備の耐用年数は15年と建物の耐用年数よりはすごく短い年数が定められています。
建物と建物附属設備の経費計上額を比較してみよう
それでは、建物に計上される時と建物附属設備に計上される時で1年間の経費がどれくらい違うかを設例で見ていきましょう。
- RCの建物(取得価額1410万円)と電気設備(取得価額1410万円)がある場合、1年間に減価償却費を通して経費に計上できる金額をそれぞれ算定して比較してください。
- 【解答】
RC建物の1年間の経費は30万円、電気設備の1年間の経費は94万円なので電気設備の方が64万円(94万円―30万円)も多く経費に計上できます。【解説】
<RC建物の1年間の経費>
建物取得価額÷耐用年数=1,410万円÷47年=30万円<電気設備の1年間の経費>
電気設備取得価額÷耐用年数=1,410万円÷15年=94万円
建物と建物付属設備に分けるときの問題点
新築の賃貸用不動産を取得した場合ならば、建築業者から見積書を提出してもらいそれに基づいて、建物と建物付属設備の金額を区分計上すればよいだけなのでなにも問題はありません。
問題になるのは、中古の賃貸用不動産を購入した時です。
中古の賃貸用不動産の取得の場合、不動産売買契約時に売主に対して購入当時の見積書をもらえないか確認してください。
それでも、築年数がかなり経過していたり、オーナーが転々としていた賃貸用不動産については残念ながら、購入当初の見積書はなくなっている可能性もあります。
その場合は、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼する方法なども考えられます。
ただし、鑑定評価は高額になるので、減価償却費を通して経費を多く計上するメリットと鑑定評価の費用を天秤にかけて意思決定をすることになるでしょう。
巷では、建物:建物付属設備=7:3で計上する方法が推奨されていますが、まったく根拠がないです。
7:3で計上するぐらいなら、見積書や鑑定評価による区分方法によらずとも、なんらかの根拠をつけて、区分した方がまだマシでしょう。
根拠資料に多少の瑕疵があっても、説明に一定の合理性があれば、税務調査でも問題にならない可能性は残ります。
最後に本当に早く経費計上したいか考えましょう
ここまでは、建物と建物附属設備を区分することにより、なるべく早く経費に計上する方法を説明してきました。
ただし、不動産賃貸業を営んでいくことを前提とする場合、銀行融資に関しても無視できないでしょう。
経費を多く計上するあまりに、赤字になってしまったのなら目もあてられません。
全体の利益を確認しながら、経費計上を早めるかどうかを決定することをお勧めします。
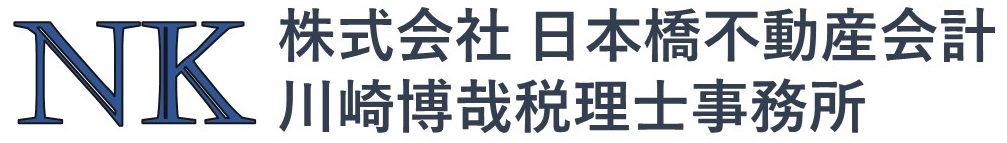











質問が来ましたので補足します。
税法上は、木造建物を除き、建物と建物附属設備の区分は「しなければならない」(義務)規定です。
ただし、実際に不動産賃貸業を行う場合、建物附属設備の金額は非常に把握しづらい(賃貸中の部屋の場合、建物附属設備の存在自体把握できないこともあります…)です。
建物と建物附属設備の区分が実際には非常に難しいなかで、どう区分していったら一番節税になるかを説明したのが今回の記事になります。