【この記事の対象者】
- 税理士がなにもしてくれないと嘆いている個人事業主
- 節税対策をどのようにしていいか分からない個人事業主
- 税理士の提案についていけない個人事業主
 くま君
くま君おさる先生!
僕が頼んでいる税理士の先生が節税対策の相談に応じてくれなくて困ってるんだけど…
違う先生に頼んだ方がいいかな?



うーん、難しい質問だね。
ちなみに、くま君、税理士さんに毎月いくら報酬払っている?



毎月2万円だよ。



うーん、それだと他の先生に頼んでも同じようになかなか相談には応じてもらえないかも…



そうなの?



その値段だと厳密には、税理士事務所の職員さんが記帳と申告をやっているはずだよ。
そうすると、職員さんは仕訳をする、申告書を作るというノルマに追われているから、節税の相談まではちょっと難しいかな…



どうすればいいかな?



考え方は2つかな。
一つ目は単純に税理士報酬の月額を上げて、税理士さんと顧問契約を結ぶこと。
二つ目はくま君自身が節税対策を自分で考えること。



税理士報酬を今上げるのは結構きついかな…
でも、自分で節税対策なんて考えられるの?



最近ではネットで情報も溢れているから、自分で取捨選択できれば、節税対策も自分でやった方が効率的かもよ。



そうなんだ。



じゃあ、今回は節税対策のもとになる考え方を2つだけ教えるよ。
この2つが理解できれば、後は自分にあった節税対策を当てはめていくだけだよ。



それは是非教えてほしいな。
税理士事務所任せが一番危ないかも…
「うちは税理士先生に記帳と申告を任せているから大丈夫だよ!」という個人事業主の方がよくいます。
では質問をかえて、「納めた所得税の金額は本当に節税を考えた金額ですか?」と聞かれても「大丈夫だよ!」と言えるでしょうか?
なぜこんな質問をしたかというと、税理士事務所の仕事は「適正な」税務申告を納税者に代わって行うことだと知って欲しかったからです。
「適正な」というのは、税法上は正しいという意味で「節税対策をしてくれる」という意味ではありません。
税理士事務所の職員はあくまで会社員なので、売上を上げるためにノルマを達成することが営業目標です。
例えば月に30件、100万円売上を達成したことが税理士事務所員の評価の対象になります。
仮に、「本当はこうしたらもっと納税額が下がるのにな」と思っても、評価の対象にならないのに、個人事業主の方に対して、税理士事務所の職員さんは節税の提案をしてくれるでしょうか?
節税のための所得税の勉強は自分でやるしかない
残念ながら、個人事業主のお客様の月額の支払い額では、記帳して申告書を税務署に提出してもらえても、節税のための税務相談まで税理士にお願いするのは無理があります。
また、契約を結んだ税理士側にも節税を指南する意思はないでしょう。
そうすると、少しでも節税対策を取りたい個人事業主の方は自分で勉強しなければならなくなります。
そこで、今回は節税対策の大枠の考え方を説明しようと思います。
これさえ知っていれば、後はあなたに当てはまる所得税の節税対策を個別に検討していくだけです。
個別の節税対策については、ブログの中にも紹介してますし、他にもいろいろな本で紹介されているのでここでは割愛しますが、大枠の考え方を知らないと間違った方向にいってしまうので、しっかり理解しましょう。
まずは所得の種類です
個人事業主が納める税金が所得税ですが、所得税の種類は次の10種類に分解できます。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 不動産所得 | 不動産賃貸業の所得 |
| 事業所得 | 個人事業主が商売をして稼いだ所得 |
| 給与所得 | サラリーマンの収入や役員の報酬 |
| 利子所得 | 預金などの利息 |
| 配当所得 | 株式などの配当収入 |
| 退職所得 | 退職するときにもらえる所得(退職金や小規模企業共済の解約金など) |
| 譲渡所得 | 土地・建物を売却した時の所得 |
| 一時所得 | 満期保険金を一回で受領した場合の所得等 |
| 山林所得 | 農業や林業を営んでいるときに得られる所得 |
| 雑所得 | 上記の9つ以外の所得 |
節税対策のためだけなら個人事業主は「事業所得」の理解が必要と覚えておきましょう。
なお、不動産賃貸業の方は「不動産所得」の理解が必要になります。
その他の所得は出てきた時に勉強すれば十分です。
大切なのは、個人事業主の所得は収入金額―必要経費で計算されるということだけです。
まず、収入金額と必要経費が区別できないようなら簿記3級程度の勉強だけはしてください。
節税対策のもとになる考え方は2種類のみ
世の中ではたくさんの節税対策が紹介されていますが、結局、節税対策の大元の考え方は次の2つのみです。
- 所得税の課税を遅らせる
- 所得税が減税される
所得税の課税を遅らせる
個人事業主の所得は年度によってばらつきがあります。
今まで仕事をくれていた会社が倒産したり、事業から撤退したりいろいろなケースが考えられます。
黒字(利益)の場合は、税金を払わないといけないのですが、赤字(損失)の場合でも、事業を継続するためには、運転資金等が必要になるため、黒字の時に課税される税額を少なくして、少しでもお金を残したいと考えるのが普通でしょう。
個人事業主にとって、お金が手元にあることが最大の商売の強みになるからです。
だから、可能であれば、黒字の時の所得税の課税をなるべく遅らせる対策をとりたいわけです。
所得税が減税される
個人事業主にとって、一番ありがたいのは本来支払うべき税金を支払わなくてよくなることです。
減税の考え方としては、各所得区分(事業所得や給与所得など)で決められている控除額(例:青色申告特別控除65万円)を使用することや、一時所得の場合に税額が2分の1になる制度を利用して、所得税の納税額自体を減らすことです。
節税対策の具体例(保険の場合)
所得税の課税を遅らせると所得税が減税されるが大元の考え方だと分かったので、節税対策の代表例である共済を使った具体例でイメージ作りをしてみましょう。
所得税の課税を遅らせる具体例
こちらの具体例として、経営セーフティ共済を思い浮かべてください。
経営セーフティ共済では払った掛け金が事業所得の必要経費に算入でき、解約して戻ってきた金額は事業所得の収入とみなされます。
今期の途中で予想外に利益が出る見込みだと分かった場合に、240万円まで経費算入でき、解約するまでに上限で800万円まで経費算入できるのでかなり便利です。
また、4年弱で解約したときも掛け金の100%が返還されるので、普通の保険よりもかなり優秀です。
使い方としては、利益が出る時に掛け金を払って必要経費に算入し、損失がでるようなときに解約すると所得税の課税を遅らせられます。
所得税が減額される
こちらの具体例として、小規模企業共済を思い浮かべてください。
小規模企業共済の場合、払った掛け金が小規模企業共済等掛金控除として所得金額(利益金額)から控除できます。
今期の途中で予想外に利益が出る見込みだと分かった場合に84万円まで所得金額(利益金額)から控除することができます。
任意解約の場合は20年以上契約期間がないと少しマイナスになりますが、事業を廃止した場合などは5年以上経過していれば、掛金の100%以上の割合でお金が返ってきます。
なお、1年で84万円まで所得金額からの控除対象となりますが、解約金は所得税の退職所得の対象になるので、退職所得控除の金額(20年までは40万/年、20年以降は70万/年)にしておくと、最終的に無税になり、所得税を減額させる効果があります。
まとめ
節税対策のためには、必ず「所得税の課税を遅らせる」と「所得税が減税される」が大元の考え方だということを覚えておいてください。
そのうえであなたが関係する所得の種類と計算方法をざっくり分かれば、節税方法を見聞きした時に正しい理解ができます。
くれぐれも税理士事務所と同じ立場に立ち、所得税法の枝葉末節の議論にならないように注意が必要です。
税務申告をするための細かい議論は税理士事務所に任せて、あなたは節税のための方策を考えるというのが個人事業主にとって最も良いサイクルになるのではないでしょうか。

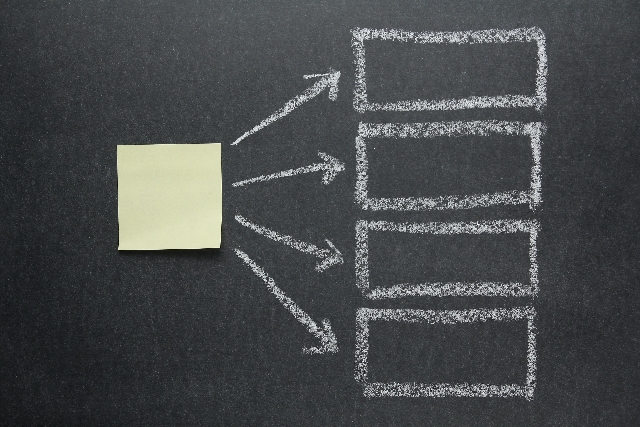
コメント