公認会計士・税理士事務所を10年経営して、また、自分が実際に不動産業務に関わってきた知識や経験を活かして、「不動産業を営む小規模会社の経理・税務マニュアル」をまとめてみたいと思いました。
今回は、その第5回目で、小規模会社の経営者に必要な経理・税務業務の知識と管理体制についてまとめます。
今回の記事は、不動産業でなくても小規模会社(目安:従業員10名未満)であれば、どの会社でも関係してくる記事になります。
他業種の方も含めて小規模会社の経営者に必要な経理・税務業務の知識と管理体制について知りたい人はぜひご覧ください。
経営者に必要な経理・税務業務の知識
小規模会社を運営する上で、①日々の取引を仕訳という形で記帳すること、②事業年度が終了した後に法人税・消費税等の確定申告書を作成することは非常に重要な経理・税務業務になります。
会社の経理・税務業務は社内の経理担当者や社外の税理士に任せることが一般的ですが、小規模会社の場合、経理業務が正確に遂行されているか、適切な税務判断が行われているかは、経営者が管理することになります(他に出来る人がいれば良いのですが…)。
よって、最低限の経理・税務知識を経営者が持ち合わせていなければ、管理体制の構築に失敗し、経理処理のミスの頻発や節税対策が取れないことによる利益の逸失を招くことになります。
経理知識について
まずは、経営者に必要な「経理」知識についてですが、日商簿記3級程度の知識があれば十分です。
現役の経営者ならば、日常業務の中で既存の仕事に必要な経理知識を身に着けていることも多いですが、簿記の本などで日商簿記3級程度の知識を網羅的に再確認できれば、経理担当者からの報告や税理士からのアドバイスをより理解し易くなります。
税務知識について
次に、経営者が必要になる「税務」の知識ですが、日常業務の中で経理担当者や税理士から聞いた知識をストックすることである程度入手できます。
ただし、経理担当者や税理士は、どちらかというと保守的な立場にあり、話す税務知識の内容についても保守的になりがちです。
経営判断や節税対策をする時に保守的過ぎると逆に業務が停滞したり、節税対策の機会を逃すこともあるので、ご自身でも積極的に税務知識を身に着けていった方が良いでしょう。
例えば、節税対策について税理士と話し合う場合、節税対策にはグレーゾーンのものがあり、合法でも、リスク管理のため税理士側からは提案したくないものがあります。
仮に、経営者の側で提案をしてくれれば、リスクを説明の上議論ができるかも知れません。
税務知識を身に着けることは、経理知識を身に着けるより時間がかかります。
当会計事務所のホームページでも税務知識に関する記事を沢山書いてます。
参考までに最重要記事を↓に挙げておきますので、良かったらご覧下さい。



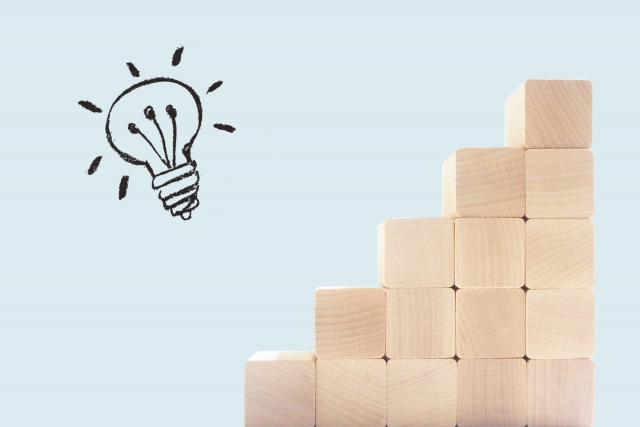
経営者が整えたい経理・税務業務の管理体制
小規模会社の場合、①会計ソフト(弥生会計・Freeee・マネーフォワード等)、②税務ソフト(達人シリーズ等)、③給与ソフト(弥生給与NEXT等)さえ使用すれば、経理・税務業務の大枠が出来ます。
ただし、経理業務が正確に遂行されているか、適切な税務判断が行われているかは大枠が出来ているかと別問題です。
いくらシステムで大枠が出来ていても、それを利用するのは、社内の経理担当者や社外の税理士です。
その利用者に対する管理体制がきちんと整えられていないと、大枠が出来ていても中身はぐちゃぐちゃという状態になります。
よって、経営者は経理・税務の管理体制をきちんと整えていくが大切になります。
経理・税務の管理体制は次の2つに区分できます。
- 社内の経理担当者の作業に対する管理体制
- 税理士事務所の作業に対する管理体制
社内の経理担当者の作業に対する管理体制
経理担当者がいる会社であれば、日々の取引を仕訳の形で記帳する業務は、経理担当者が行うことになります。
実は、この仕訳というものが、経理・税務業務のキモになります。
仕訳が間違っていれば、最終成果物である法人税・消費税等の確定申告書も間違っていることになります。
よって、仕訳が間違えないようにチェックする管理体制を整えていくことが最も大切になります。
具体的な管理体制を構築するために必要になるチェック項目は次の2つです。
- 仕訳を行う経理担当者に経理・税務の最低限の知識があるか?
- 仕訳をした人の自己チェックと上席者のダブルチェックを行っているか?
仕訳を行う経理担当者に経理・税務の最低限の知識があるか?
仕訳を行う経理担当者に経理・税務の最低限の知識がないとまず正確な仕訳はできません。
最近の会計システムでは、領収書などを読み込めば推定仕訳まで作成してくれる機能もありますが、残念ながら今のところ精度はまだまだ高くありません。
推定仕訳機能はアシスト機能としては十分な機能ですが、ちゃんとした知識がある経理担当者がいないとまだまだ自動で仕訳を作成してくれるレベルには到達していません。
現状で大切になるのは、経理・税務の知識を持った「人」になりますので、くれぐれも軽視しないようにしたいところです。
仕訳をした人の自己チェックと上席者のダブルチェックを行っているか?
経理担当者がどんなに優秀でも、人間である以上必ず仕訳の間違いは出てきます。
仕訳の間違いを失くすこと自体はできませんが、後で自分で発見したり、他の人が発見することは可能です。
自己チェックは仕訳を入力した直後ではなく、必ず一日程度、時間を空けて実施してください。
仕訳入力後、すぐに自己チェックを実施すると、頭の中が同じ間違い理論でチェック作業が進んでしまいますので、まずエラーを発見できません。
ダブルチェック機能については、必ず実質があるものにしてください。
上席者の確認印があるのに、内容を全くチェックしていない例をよく見かけます。
何のためにチェックをしているのかを必ず確認の上、確認項目が多くなりすぎて上席者の業務が圧迫されるようであれば、ダブルチェックの金額を決めて、その金額以上のものをきちんとチェックするという体制を整えるのでも良いでしょう。
大切なのは、誰が仕訳について責任を持つかの取り決めです。
責任が社内で曖昧になると間違った仕訳を発見することはできません。
税理士事務所の作業に対する管理体制
税理士事務所は経理・税務業務を専門として日々業務を行っているので、当然ですが、自分達で自己チェック機能やダブルチェック機能を保持しており、そこまで大きな間違いは起こしません。
ただし、税理士事務所で貴社の仕訳を担当している人は、必ずしも税理士とは限りません。
近年は経理・税務業務に対する委託報酬が大幅に下落しており、アルバイトが仕訳をしたり、上席者のダブルチェックの関与時間が大幅に削減されている可能性があるのも事実です。
そこで、大規模な間違いを未然に防ぐためにも、残念ながら最低限の品質チェックを会社側で行うことが必要になります。
少なくても、仕訳を実施する担当者の資質と委託先の税理士事務所の品質管理体制(自社に対して最大どのくらい時間が割けるのか、上席者のダブルチェック体制はどうなっているのか)は確認しておきましょう。


コメント