弥生会計などの会計ソフトの進化により、近年では、仕訳の入力方法が多彩になっています。
例えば、IT技術を利用して、銀行口座と会計ソフトを自動連携したり、銀行からデータで貰った預金明細を会計ソフトに直接取り込んだりして、自動的に仕訳を作成してくれる技術もあります。
ただ、FINTECH(フィンテック)やクラウド会計などの横文字が独り歩きをしていて、肝心の中小企業(個人事業主を含む)で「どうやって新しい仕訳の入力方法を取り入れていくか?」の議論は中々進んでいません。
そこで、今回は中小企業(個人事業主を含む)で行える最も効率的で簡単な新しい預金仕訳の入力方法について考えていきたいと思います。
ちょっとの差で、あなたの会社(個人事業主の場合は事業)の預金仕訳の入力作業を一気に減らせるかも知れません。
- 会計ソフトが標準装備している、①仕訳自動作成機能を利用しつつ、②足りない部分だけ人が仕訳を入力すれば、今までより簡単にミスなく預金仕訳の入力作業が出来ます。
預金仕訳の入力方法を見直そう!
中小企業(個人事業主を含む)が1年間に行う仕訳は期中の①預金に関する仕訳と②現金に関する仕訳が大部分を占めています。
その中でも、預金に関する仕訳は、件数が多いだけでなく、1件あたりの金額も多額になります。
近年、預金に関する仕訳については、IT技術を利用して、①銀行口座と会計ソフトを自動連携して仕訳を作成する方法、②銀行からCSVデータ(エクセルデータみたいなもの)を入手して、直接会計ソフトに取り込む方法など人が仕訳を入力しなくても自動で仕訳を作成してくれる方法があります。
もし、IT技術を利用した自動仕訳入力方法が採用できれば、①仕訳入力作業の時間が短縮でき、②人の手を介さないため仕訳入力ミスも減らすことができます。
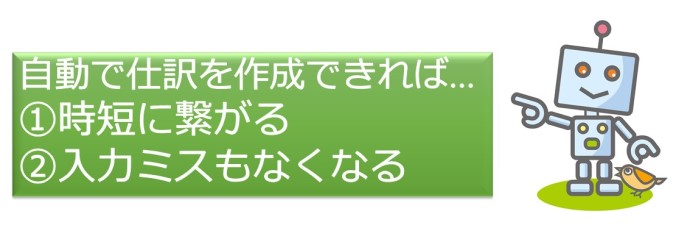
例えば、あなたの会社の1か月の預金仕訳の件数が300件だったとします。
人の手で1つ1つ入力すると、1仕訳あたりの入力に1分かかりますので、全体で300件×1分=300分(5時間)の時間を費やして預金仕訳を行うことになります。
しかし、会計ソフト(弥生会計など)の自動で仕訳を作成してくれる機能を利用すれば、人の手で入力する時間の半分程度で預金仕訳が完成します。
つまり、300件×1分÷2=150分(2時間半)程度で預金の仕訳入力作業が終了することになります。
自動で仕訳を作成してくれる機能を利用すれば、準備を含めて丸1日作業だった預金の入力作業が午前中で終わることになります。
同時に、金額入力など人の手で行うとミスが多い作業を会計ソフトが自動で行ってくれるので、仕訳入力ミスも減少します。

まだあなたの会社が会計ソフトの預金仕訳自動作成機能(例えば、弥生会計では、「スマート取引取込」という名前で標準装備されている)を利用していないならば、利用を検討する価値は十分にあるでしょう。
[br num=2]
あなたの会社とってベストな仕訳入力方法は?
預金仕訳を自動化できれば、時短になり、さらに業務効率も上がることが分かりました。
では、あなたの会社で預金仕訳の自動化をどのような方法で進めていくべきでしょうか?
この答えを出す前に現在採用できる預金仕訳の入力方法を確認しておきましょう。
[br num=1]
- 1行ずつ手で仕訳を打ち込んでいく方法(従来の入力方法)
- 金融機関と会計ソフトを「直接」連携させ、預金仕訳を作成する方法(完全自動化)
- 金融機関から入手したCSVを会計ソフトに取り込んで仕訳を作成する方法(半自動化)
[br num=1]
1行ずつ手で仕訳を打ち込んでいく方法(従来の入力方法)
会計ソフト(弥生会計など)を普通に立ち上げて、1行ずつ手で仕訳を入力していく方法です。
現状どこの企業でも行われている最も一般的な方法でしょう。
この方法を採用するメリット・デメリットは以下のようになります。
[br num=1]
- どんな仕訳でも入力できる(例えば、勘定科目が2つ以上になっても入力できる)。
- 金額の入力ミスが生じる可能性がある。
- 会計ソフトに人が入力する箇所が多く煩雑である。
[br num=1]
金融機関と会計ソフトを「直接」連携させ、預金仕訳を作成する方法(完全自動化)
金融機関の預金口座情報を会計ソフトと「直接」連動させ、自動で仕訳が作成されるようにする方法です。
[br num=1]
- 預金勘定の相手科目以外を自動で作成してくれるので、仕訳入力の時短に繋がる。
- 日時を指定しておけば、勝手に仕訳を作成してくれるので、仕訳計上漏れがほぼなくなる。
※ 預金勘定の相手科目だけは預金通帳から分からないので、経理担当者が手で入力することになります。
- 預金通帳の入出金データ1行につき、1つの仕訳のため、勘定科目が複数にまたがる仕訳には対応できない。
- 会計ソフト会社のホームページに金融機関の情報(IDやパスワード等)を入力しなければならない。
[br num=1]
金融機関から入手したCSVを会計ソフトに取り込んで仕訳を作成する方法(半自動化)
金融機関から預金明細をCSV(エクセル表みたいなもの)で貰い、CSVを会計ソフトに取り込んで仕訳を自動で作成する(半自動化)方法です。
なお、完全自動化は、金融機関と会計ソフトを「直接」連携させるのに対して、半自動化は完全自動化と違い、①CSVデータを金融機関から貰い、②貰ったCSVデータを会計ソフトに取り込むという「間接」連携になります。
[br num=1]
- 預金勘定の相手科目以外を自動で作成してくれるので、仕訳入力の時短に繋がる。
- 完全自動化と違い「間接」連携のため、金融機関の情報(IDやパスワード等)を会計ソフト会社のホームページに入力しなくても良い。
※ 預金勘定の相手科目だけは預金通帳から分からないので、経理担当者が入力することになります。
- 入出金データ1行につき、1つの仕訳のため勘定科目が複数にまたがる仕訳には対応できない。
- 完全自動化よりCSVデータを会計ソフトに取り込む分だけ手間がかかる。
[br num=1]
どのような方法で預金仕訳の自動化を進めていくか?
では、どのような方法で預金仕訳を入力していくと良いでしょうか?
結論から言うと、完全自動化又は半自動化で大部分の仕訳を作成しつつ、従来の入力方法で足りない仕訳を作成していくことになります。
その場合、以下の論点が発生するはずです。
- 完全自動化と半自動化のどちらを採用するのか?
- なぜすべて自動化できず、従来の入力方法(手動仕訳)が必要になるのか?
[br num=1]
完全自動化と半自動化の選択基準について
「完全自動化と半自動化のどちらを選択するか?」については、会計ソフト会社のホームページに金融機関の情報(IDやパスワード等)を入力することに対する考え方次第でしょう。
おそらく、会計ソフト会社でも、お客さんから金融機関の情報を入手する以上、セキュリティー対策は万全でしょうし、故意・過失による情報漏洩の際は規約に関わらず会計ソフト会社が責任を負うことになるはずです。
ただ、保守的な利用者であれば、金融機関と会計ソフトの連携の技術的な仕組みが理解できない以上不安は残るはずです。
現に私は保守的な利用者なので、どのクライアントでも完全自動化には踏み切れていません。
ただ、会計ソフト会社の研修に参加したり、完全自動化の資料を貰う限り、半自動化よりかなり便利に見えることも事実です。
どちらを選択するかの基準ですが、完全自動化のセキュリティーにあなたが少しでも不安を感じるようならば、半自動化を選択するべきです。
[br num=1]
なぜすべて自動化できず、従来の入力方法(手動仕訳)が必要になるのか?
完全自動化又は半自動化にすれば、預金に関する仕訳はほとんど作成できてしまいます。
ただし、残念ながら、従来通り、1行ずつ手で仕訳しなければならない場合も出てきてしまいます。
つまり、預金口座の入出金が一行だけでも、それを仕訳に表すと複数の勘定科目が出てきてしまう場合です。
例えば、給与支給の仕訳です。
[br num=1]
|
借方
|
金額
|
貸方
|
金額
|
|---|---|---|---|
|
給与手当
旅費交通費
|
80万円
2万円
|
普通預金
預り金(源泉等)
|
75万円
7万円
|
[br num=1]
上記の給与支給の仕訳では、借方・貸方でそれぞれ2つずつの勘定科目が発生していますが、金融機関口座の出金欄では75万円しか出てきません。
完全自動化又は半自動化で仕訳を作成した場合、給与支給の仕訳を75万円の1行で行うことを求められますが、それは不可能です。
この場合、①完全自動化又は半自動化で取り込んだ仕訳データの該当箇所(上記給与支給の仕訳の場合75万円の出金仕訳部分)を削除し、②会計ソフトに正しい仕訳を人が手で入力することになります。
中小企業(個人事業主を含む)の場合、大多数は1行仕訳でそのまま自動化できるのですが、少数ながら2行以上の仕訳が出てきてしまいますので、従来の方法(手動仕訳)を行う必要が出てきます。
[br num=1]
まとめ
今回、最新の預金仕訳入力方法を解説しましたが、会計ソフト会社は、まだまだ技術的に進歩させようとしています。
よって、預金仕訳入力の自動化は益々進歩して、簡単になっていくと思います。
ただし、よほどの技術革新が起きない限り、当面は今回説明した3つの方法以外の仕訳入力方法が出てこないでしょう。
もし、あなたの会社(個人事業主を含む)の預金仕訳を手で入力しているようならば、一度仕訳自動化を含む、仕訳入力方法の改善を考えてみる頃合いかもしれません。


コメント